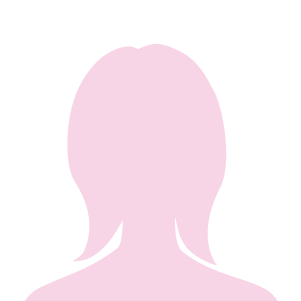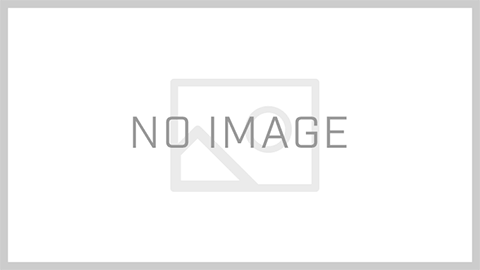この記事では、子供の死を受け入れられないあなたへ向けて、毎日を生きるためにすべきことを紹介します。
愛するわが子を亡くし、毎日を生きるのに必死ですよね。
夢も希望もどこかへ行ってしまい、真っ暗なトンネルの中にいるようなそんな感覚になります。
むしろ生き残ってしまった自分が悪いんだ、そんな気持ちにすらなってしまいます。
本記事で伝えたいこと
- 毎日をどう生きたらよいか
- 子どもの死とどう向き合ったらよいか
- 心が癒された本やDVDの紹介
あなたと同じような境遇の親として、経験をもとにしながら生きるためのヒントを書きたいと思います。
同じように愛するお子さんを亡くして、苦しんでいるあなたに届きますように。
目次
子供の死を受け入れられない

- 夢
- 希望
- 幸せ
- 家族団らん
- 楽しい
- 美味しい
- 嬉しい
昨日まで楽しく、家族仲良く暮らしていたのに今日からはもう二度と一緒にいられなくなります。
ある日突然入院となったり、交通事故になったりして、元気な子供とは会えなくなってしまうのです。
もう二度と。
子供との突然の別れ
交通事故のように、突然の別れはなんとも言葉がありません。
「行ってきます」と家を出て、「さようなら」を言うこともない突然の別れ。
残された親は、あの時あぁしてあげればよかったと後悔することしきりだと思います。
あまりに突然で、そのショックは計り知れないものでしょう。
闘病の末の別れ
大病にかかり、長きにわたり闘病生活を送るため入院生活を送る子もいます。
入院すると、それまでの自宅で家族仲良く過ごすという生活から一転。愛する我が子に、検査や治療で痛いこと辛いことをたくさんさせてしまいます。
それを見てるしかないのは、本当にいたたまれない気持ちになります。
そしてそんなにも頑張ったのに!死んでしまうというこの世の悲劇。
生きる希望もなにもかも感じなくなって、この世に生きている意味さえないと思うようになります。
ショックでうつ病になる方もいらっしゃると思います。うつ病から生きるためにできることについては、こちらの記事で紹介しているのでご覧ください。

子供の死を無理に受け入れようとしなくて良い

- 笑っちゃいけない
- 楽しんじゃいけない
- 美味しいものなんか食べちゃいけない
そんな風に思ったこと、ありませんか?
そんな心境になるのは、あの子が死んでしまったのに、生き残った私がこんなことしてはいけないという思いからではないでしょうか。
それは、当然の反応です。
だけどそんな時、周囲はあなたに励ましの言葉をかけてきますよね。
お前に何が分かる?
私は励ましを受けるたび、そう思っていました。
子どもを亡くすという経験をしていない人に何を言われたところで、心にはまったく響きません。
愛する子供が死んでしまったという悲劇から立ち直ることなんて、簡単にはできません。時間が解決してくれるものでもありません。
だから、あまり周りの言葉に振り回されないでください。
あなたがそろそろ頑張らないといけない理由なんて、一つもありません。
耳を塞いで、閉じこもっても良いから自分の身を守りましょう。
子供の死を受け入れられないけど生きなければ

だけど、子供の後を追うようなことはしてはいけない。そんなことをして、あの子が喜ぶのでしょうか?
自分の命を絶ってはいけません。
私はよく、こう思って日々生きています。
自分が死んで天国へ行った時、また娘と再会できるように。そんな淡い希望を胸に、日々生きています。
そう思うと、変なことはできないと身が引きしまる思いがします。
子供の死を受け入れられない中で生きるためにできること

では辛い思いを背負いながら、どうやって毎日を生きていったらよいのでしょう?
子供を亡くした親御さんたちは、皆同じようなことを思いながら必死になって今日という日を生き抜いているでしょう。
自分が今できることをやる
もうずっと部屋を暗くして、一日中泣いて暮らしていたいぐらい。
そんな中で仕事に行ったり、手続きへ出かけたりするのは本当にしんどいですよね。
今あなたがやれることを淡々とやる、これにつきます。
淡々とやれることをやっていると、何の意味があるのかなんて考える間もなく時が過ぎていきます。
もし何かすることが辛すぎて、あなたの家族に代わってもらえるならお願いするのもアリです。
泣きたいときは、思いっきり泣いていいんです。
そうやって毎日泣きながらでも、今あなたにできることをやるしかないです。
同じような境遇の方と触れ合う
一人で家にこもっていると、どんどん気持ちが落ち込んで潰れてしまいます。
私が良いと感じたのは、同じようにお子さんを亡くされたご家族と交流したことです。
何も言わなくても、共に泣き、ただそばにいるだけで気持ちが癒されてきます。
病院やお寺さんによっては、グリーフケアの会を開いているところもあります。
グリーフケアの会で、そういったご家族と会う機会が生まれます。
いずれにしても同じような境遇の方との交流は、きっとあなたの心の支えになるはずです。
有名な「風の電話」はグリーフケアの効果もあると思います。風の電話については、下記の著書をご一読いただければと思います。
本を読む
一冊目は、風見しんごさんの「さくらのとんねる 二十歳のえみる」です。
娘さんが亡くなってからの生きる葛藤や心の思いなど、同じ境遇の親として共感できる部分がたくさんありました。
風見さんの本を読むことであなたが救われる部分もあると思いますが、表現によっては辛い気持ちになる部分もあるでしょう。
まだお子さんを亡くされて日の浅い方は、読んでいて辛くなることも予想されるのでご無理のない程度に読んでいただければと思います。
今すぐ読まなくても良いので、あぁこんな本もあるんだなと心のどこかに置いておけば良いと思います。
二冊目は、「喪失とともに生きる 対話する死生学」です。
こんなにも患者を思い、また家族のそばにいてくれる医療職がいるのだということに驚かされます。
こちらも表現によっては、お子さんのことを思い出して辛くなる場合も考えられます。どうぞご無理のない程度に読んでくださいね。
DVDを観る
死んだ人は二度死ぬともう戻ってこれないと言います。
一つはこの世で命を落とした時、二つ目は死者について誰も話をしなくなった時。
アニメですが、亡くなった子どもたちと私たち遺族の気持ちを思い描いている、素晴らしい作品でした。
亡くなった子どもたちのことを語り継いでいくこと。
私たち遺族にとって、それが大切なことなんだと実感できました。
リメンバーミーは、Amazonプライムで見ることができます。
ブログを読む&書く
アメブロなど探していると、お子さんを亡くした親御さんが書くブログがけっこうあります。
どの方も子供を亡くして辛いという思いを綴っておられ、同じ遺族として共感できる部分がたくさんあります。
あなたがブログを書いて、辛い気持ちをつづるのも良いでしょう。同じ仲間同士、きっと優しいつながりができます。
お子さんがつないでくれた、ご縁です。
私も娘のことをブログに書いています。よろしければ、こちらからご覧ください。
何か行動してみる
もしあなたがいろんな方と交流したり本やブログなどを読んだりして、少しずつ日常を取り戻しつつあるとしたら何か行動してみるのも良いかもしれません。
- 輸血のお返しに献血に行く
- ヘアドネーションする
- 自分の思いをブログに書く
ヘアドネーションとは、抗がん剤などの影響で髪の毛が抜けてしまった子供たちに贈る善意のプレゼント。
自分の髪の毛を切って、医療用のウィッグとして使ってもらうのです。
ヘアドネーションについて詳しくは、「ヘアドネーションを待っている人|あなたの善意は彼らに届く」こちらの記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

また自分の思いをブログに書くことで、今苦しんでいる方やこれから辛い思いをする方の心の拠り所となる可能性が生まれます。
あなたの気持ちが落ち着いて、「やってみよう」と思ってからで良いです。決して無理しないでくださいね。
子供が死んでもメッセージは受け取れる

子供が亡くなり姿が見えなくなったとしても、きっと子供たちに会える瞬間があります。
- 車を運転していてふと前を見たら、前の車のナンバーが子供の誕生日だった
- ふと手に取ったパッケージに、子供のあだ名が書かれていた
- すれ違った人の顔が亡くなったあの子に似ていて、そっと後ろ姿を見守った
なんだかうまく言葉にできないけれど、そういった不思議な経験をされる方が多いです。
子供の死を経験していない人からしたら、そんなの偶然だというかもしれません。
でも子供の死を経験した私たちからしたら、きっとあの子からのメッセージなんだと感じるんですよね。
そういうあの子を感じられる瞬間にたくさん出会えると、励まされるようになります。あぁ今日はここで出会った、明日はどこで出会えるかなと少し楽しみをもてたりします。
あまりキョロキョロしすぎて、事故しないようにしてくださいね。
子供たちはあの世でじっとしているのではなくて、姿こそ見せないけれど私たちのそばで見守っていてくれるんだなぁと感じます。
それは子供を亡くした親たちにとって、あの子を感じられるせめてもの貴重な瞬間なんです。
死んでも子供とはいつまでも一緒だよ
以上、子供の死を受け入れられないあなたへ【毎日を生きるためにすべきこと】について私なりの所感を書かせていただきました。
子供たちの姿は見えなくなってしまい、もう一緒に話すことも遊ぶこともできないのは辛いですよね。
だけどなんとなくあの子を感じられるようなことがあると、嬉しくて心が温まります。
それは誰にも分らない、あなたとあの子だけの大切な思い出。
いつまでも私と一緒にいるんだよという、子供たちからのメッセージなのかもしれません。
毎日生きることは本当に辛いけれど、どうか心温まる瞬間があなたにもありますように。